
倉敷中央病院/水島協同病院/よこやま内科・循環器内科
倉敷地区における心不全地域連携 〜3人主治医体制によって「入院前の発見」に取り組む〜
2024年12月取材
患者さんを地域で診るために、地域と医療を繋ぐ各施設の先進的な取り組み、地域での役割など事例をご紹介します。
なお、インタビューさせていただいた先生のご所属は取材時点のものとなります。

倉敷地区における心不全地域連携 〜3人主治医体制によって「入院前の発見」に取り組む〜
2024年12月取材

日常の実臨床に生きる災害医療における薬学的管理の視点と視野
2024年11月取材

クリニックの診療の質を高めるプライマリ・ケア認定薬剤師の取り組み
2023年7月取材

患者さんのQOL向上のために腎臓病薬物療法専門薬剤師が担う役割と多職種連携、地域医療への貢献
2023年6月取材

心不全地域連携 全県一体で取り組みをスタート
2023年2月取材

感染制御専門薬剤師が主導する薬学的管理・チーム医療・地域病診薬連携の推進
2022年12月取材

感染制御専門・認定薬剤師による院内・地域への貢献、感染制御戦略の企画・立案
2022年10月取材

過疎地域を支える地域医療連携推進法人の取り組み
-地域医療の実現を目指して-
2022年6〜8月取材

高血圧診療におけるPHR管理アプリの価値
2022年6月取材
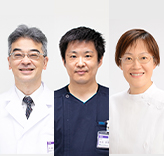
がん専門薬剤師による薬学的管理の実際と地域病診薬連携の推進
2021年11月取材

2021年10月取材

多職種連携とICTツールの可能性
2021年8月取材

薬局薬剤師の積極的な服薬フォローアップへの取り組みに向けて
2021年4月取材
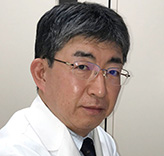
がん薬物療法を取り巻く専門医とかかりつけ医の協働
2021年1月取材
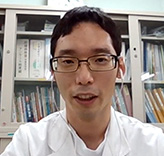
多職種による栄養サポートでサルコペニア予防と予後改善を目指す
2020年10月取材