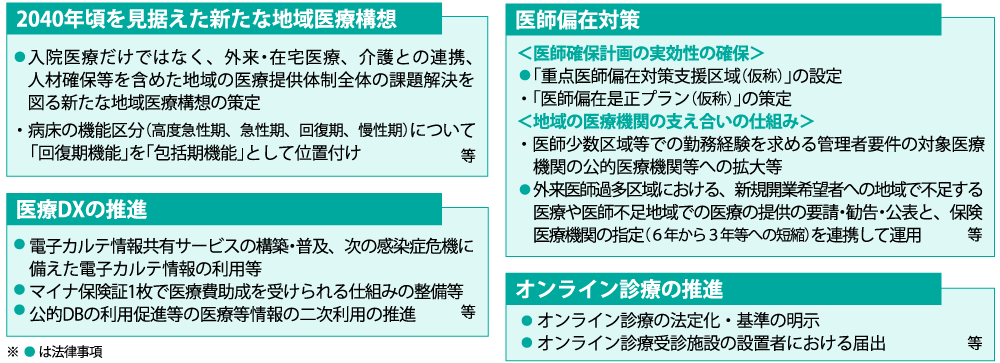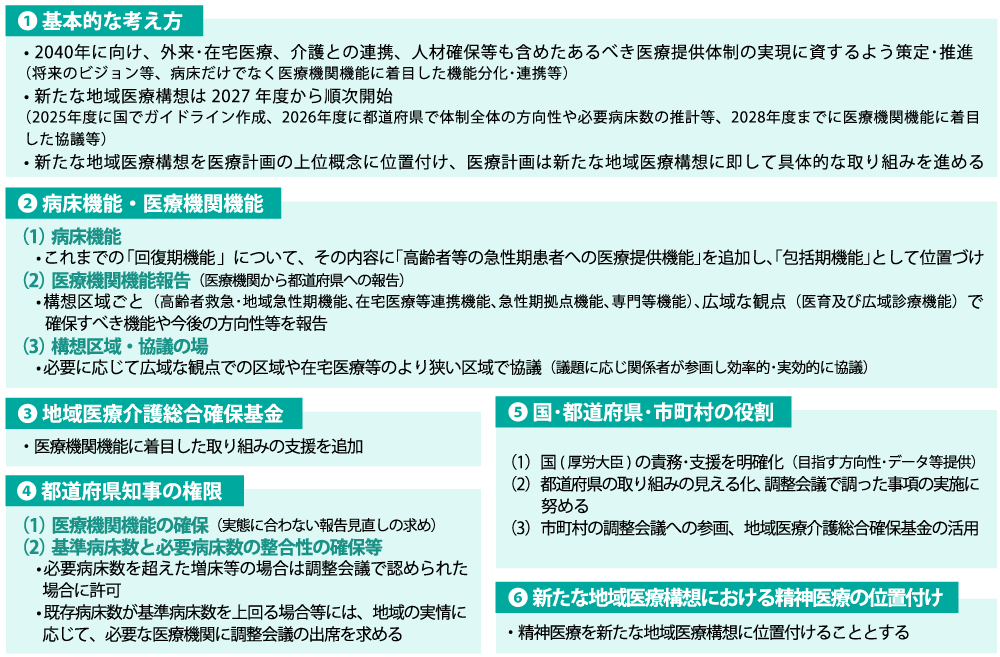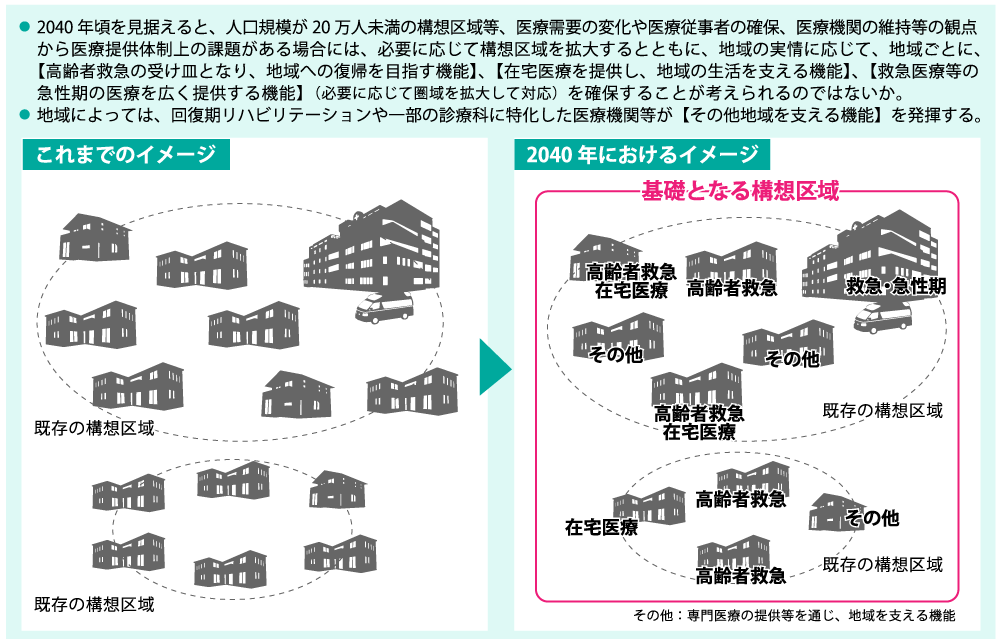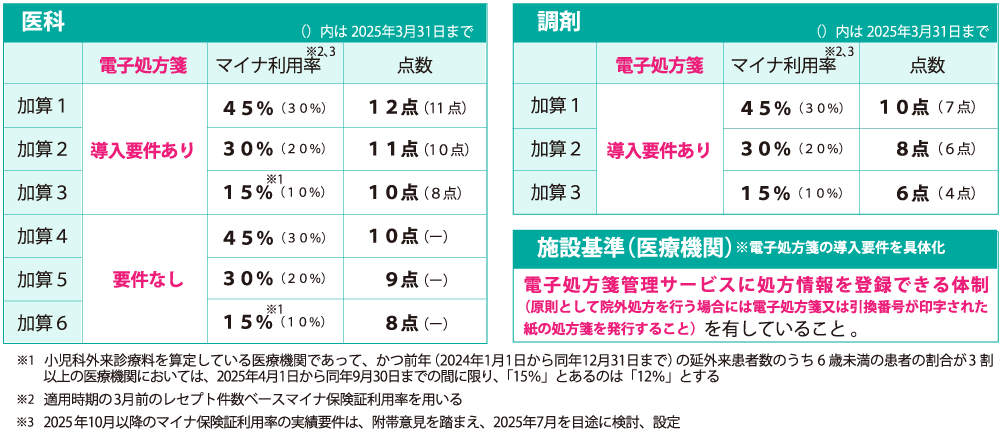【新たな地域医療構想】
政府は2月14日、医療機関機能報告制度の創設や医師偏在対策等を盛り込んだ「医療法等の一部を改正する法律案」を閣議決定し、同日に国会に提出しました。この法案では、(1)地域医療構想の見直し等、(2)医師偏在是正に向けた総合的な対策、(3)医療DXの推進-等が大きな柱となっており、2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革の方向性が示されました(図表1)。今回は「新たな地域医療構想(以下、新構想)」について確認します。
(図表1)2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革
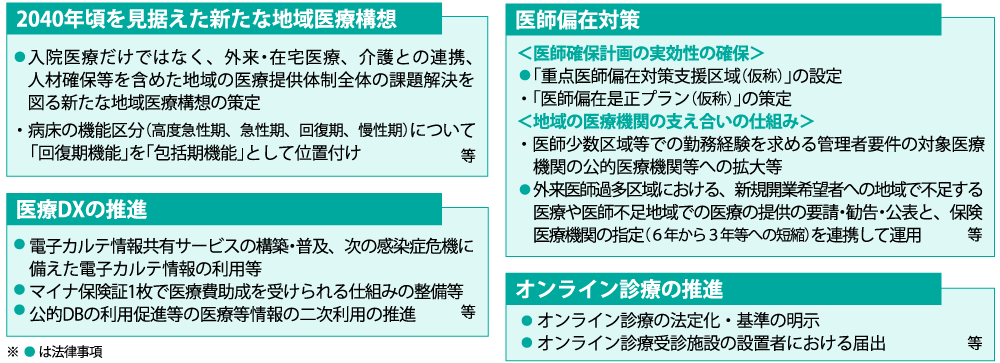
出典:厚生労働省 医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について(報告) (一部抜粋、改変)
新構想は地域の医療提供体制全体の課題解決へ
社会保障審議会(医療部会)は、2024年末に「2040年頃に向けた医療提供体制の総合的な改革に関する意見」を提示。意見では、「今後の高齢救急搬送患者の増加や在宅医療の需要拡大、生産年齢人口の減少に伴う医療従事者不足の深刻化等に対応していく為には、より質の高い医療やケアを効率的に提供する体制を構築していく必要がある」としています。
また、「新たな地域医療構想に関するとりまとめ」では、基本的な方向性として、「85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、必要に応じて入院し、日常生活に戻ることができ、同時に医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築する」と明示。
新構想では、入院医療だけでなく、外来・在宅医療、介護との連携等を含む、医療提供体制全体の課題解決を図る構想となりました(図表2)。
(図表2)新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
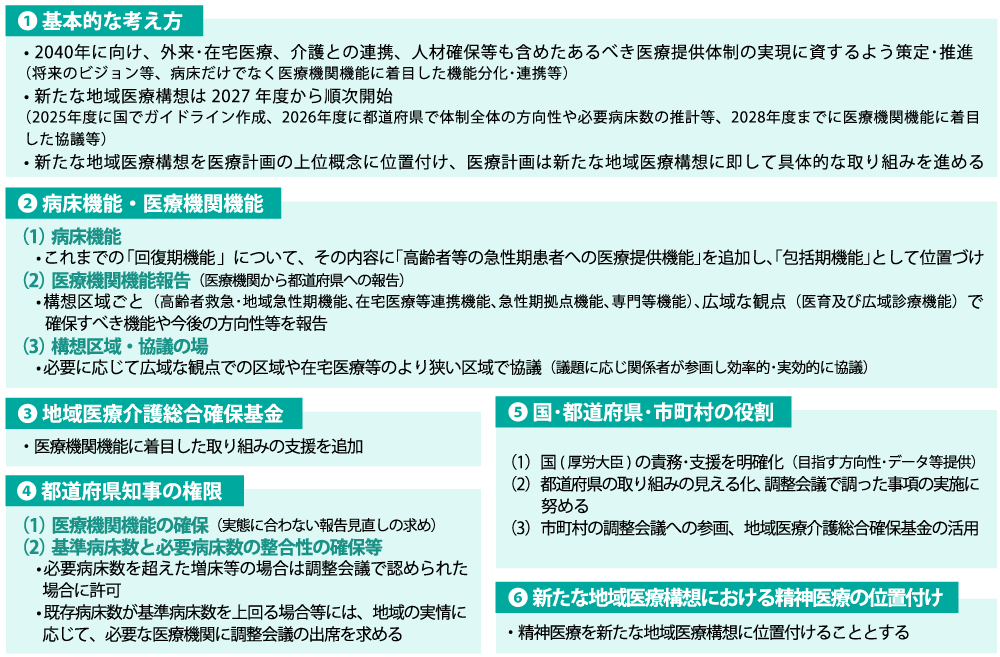
出典:厚生労働省 新たな地域医療構想に関するとりまとめ 別添2(一部抜粋、改変)
医療機関機能は構想区域単位の4機能と広域1機能に
新構想では、「医療機関機能」が最大のキーワードです。限りある医療資源を最適化・効率化しながら、「治す医療」と「治し支える医療」を担うそれぞれの医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築するため、医療機関(病床機能報告の対象)から都道府県に対して医療機関機能を報告する仕組みを創設します。医療機関機能は、次の5つを定義しています。
①高齢者救急・地域急性期機能
高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れ、入院早期からのリハビリテーション・退院調整等を行い、早期退院につなげて退院後のリハビリテーション等の提供を確保
②在宅医療等連携機能
地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設等と連携した24時間の対応や入院対応
③急性期拠点機能
手術や救急医療等の医療資源を多く要する症例を集約化した医療提供
④専門等機能
集中的なリハビリテーションや中長期にわたる入院医療機能、一部の診療科に特化し地域ニーズに応じた診療等
⑤医育及び広域診療機能
医師派遣や医療従事者の育成、広域な観点が求められる診療の総合的な提供と、都道府県との必要な連携
医療機関機能①~④は、二次医療圏等が基礎になる構想区域単位で確保する機能です。①、②は地域の実情に応じた報告が可能になるよう、報告対象の水準に一定の幅を持たせるような工夫を今後検討します。
これに対して急性期病院の集約化が目的である③の報告では、医療の地域シェア等の「一定の水準」を設定し、手術や救急等、医療資源を多く要する症例を集約。都道府県は構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するかを設定します。
⑤は広域な観点で確保する機能です。広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の状況については急性期拠点機能を担う医療機関にも報告を求め、⑤を有する医療機関とともに、地域全体で必要な機能を確保するための協議に活用します。
医療機関機能報告の内容が実態に合わない医療機関には、都道府県が報告の見直しを求めることができます。
構想区域は必要に応じ変更、調整会議は議題に応じ実施
病床機能区分ごとの必要病床数の推計及び病床機能報告は、全体で医療需要を捉える仕組みとして一定の役割を果たしてきたことから、制度を維持します。ただし、病床機能4区分のうち、これまでの「回復期機能」については、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急性期と回復期の機能を併せ持つことが重要となることを踏まえ、名称を「包括期機能」に改めます。
構想区域は引き続き二次医療圏を基本としつつ、医療需要の変化や医療従事者の確保等、医療提供体制上の課題がある場合には必要に応じて見直し(図表3)。広域な観点での区域は都道府県単位(必要に応じて三次医療圏)で設定し、在宅医療等については、地域の医療・介護資源等の実情に応じて、市町村単位や保健所圏域等、より狭い区域を設定します。
地域医療構想調整会議には、議題に応じて、医療関係者、介護関係者、保険者、都道府県、市町村等の必要な関係者が参画し、医療機関の経営状況等地域の実情も踏まえながら、実効性のある協議を実施することを求めます。
(図表3)2040年に求められる基礎となる構想区域(イメージ)(案)
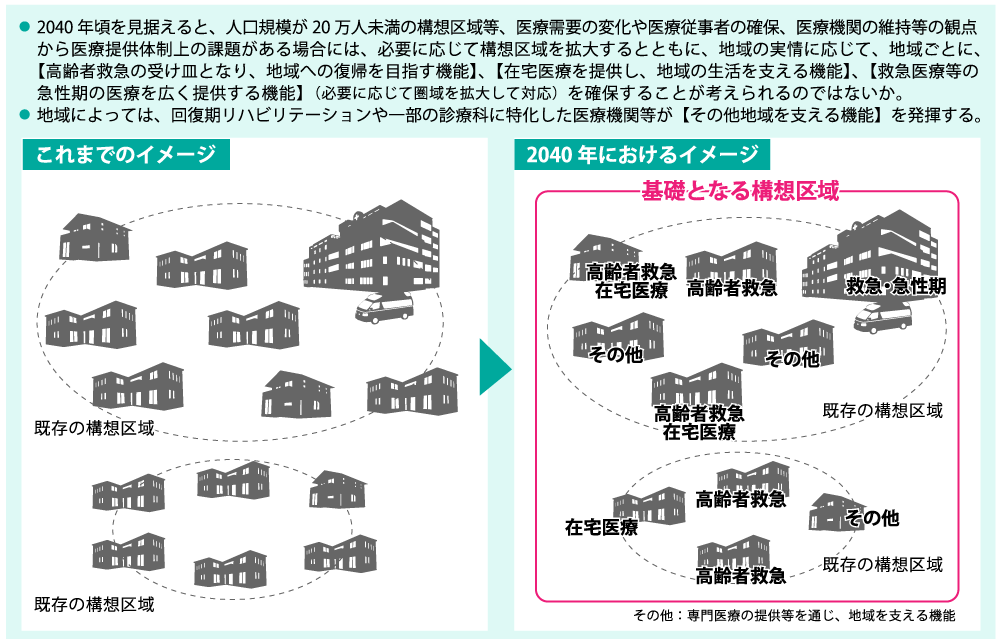
出典:厚生労働省 第9回新たな地域医療構想等に関する検討会 資料2(一部抜粋、改変)
具体策は国が2025年度に作成するガイドラインで明確化
外来・在宅医療の協議の対象となる構想区域や協議の参加者は、在宅医療については市町村単位とする等、議題に応じて柔軟に設定することを想定しています。区域ごとに議論すべき内容や議題に応じた参加者の選定、前出の調整会議で共有するデータや課題、課題を踏まえた取り組みの内容等、運用の詳細については国が2025年度に検討・作成する「新たな地域医療構想の策定・推進に関するガイドライン」で明確化します。
地域の医療提供体制全体の将来のビジョンとして医療計画の上位概念に位置付けられる新構想は、構想に沿った具体的な取り組みが医療計画等に落とし込まれます。
新構想は2027年度から順次運用を開始。医療の役割分担を地域ごとに進めるため、医療機関機能に着目した協議は2028年度までに行う予定です。
Topics
【医療DX推進体制整備加算】
厚生労働省は2月下旬、2025年4月1日から施行する「医療DX推進体制整備加算」の再編を官報告示しました。
医科は電子処方箋導入の有無別で 現行の3区分から6区分に細分化
医療機関(歯科を含む)の電子処方箋導入率は、2025年3月末時点で約10%弱にとどまる見込みで、政府目標の未達が確実です。そのほか、2024年12月には医薬品マスタの設定不備による不具合が発生する等、運用面の課題も露呈しました。
告示では、医科・歯科の施設基準における電子処方箋導入要件を、「電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋または引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること」と、より具体的な内容に変更。その上で電子処方箋管理サービスに処方情報を登録する手間を新たに評価し、導入済の医療機関と未導入の医療機関の加算点数に差をつけました。
この結果、「医療DX推進体制整備加算」の報酬体系は、現行のマイナ保険証利用率に応じた3段階の評価を、電子処方箋導入の有無でさらに2つに分割した全6区分の評価に細分化されました(図表4左)。
調剤は3区分を維持し、評価を2~3点引き上げ
2025年3月末までに80%弱の調剤薬局で電子処方箋導入が見込まれることから、電子処方箋の導入を基本とした調剤報酬の評価と位置づけ、評価区分の細分化は行いません。見直し後の点数は、紙の処方箋も含めた調剤情報登録の手間を考慮して2~3点を引き上げます(図表4右)。
このほか、医薬品マスタの適切な設定等、安全な運用を担保する対策として、電子処方箋導入済の医療機関・調剤薬局には、疑義解釈通知で厚生労働省が示すチェックリストを用いた点検の完了を求める予定です。
今後、厚生労働省は医療機関への導入促進と、電子処方箋を安全に運用できる仕組み・環境の整備に注力しつつ、2025年夏を目途に新しい政府目標を設定する方針を明らかにしています。
なお、2月末の疑義解釈において、新「加算1~3」を算定する場合は、施設基準の届出直しが必要と示されましたので、注意が必要です。
(図表4)2025年4月1日~9月30日の医科及び調剤における医療DX推進体制整備加算
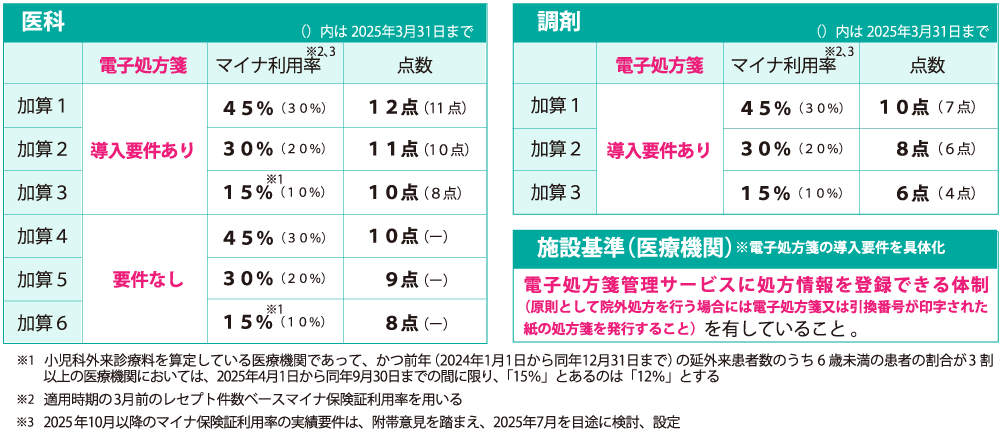
出典:厚生労働省 中央社会保険医療協議会 総会(第603回) 総-8-3(一部抜粋、改変)
(編集:株式会社日本経営)
※本稿は2025年3月6日時点の情報に基づき作成いたしました。
内容に関する一切の責任は株式会社日本経営に帰属します。また、いかなる部分も一切の権利は株式会社日本経営に所属しており、電子的又は機械的な方法を問わず、いかなる目的であれ無断で複製又は転送等はできません。使用するデータ及び表現等の欠落、誤謬等につきましてはその責めを負いかねます。なお、内容につきましては、一般的な法律・税務上の取扱いを記載しており、具体的な対策の立案・実行は税理士・弁護士等の方々と十分ご相談の上、ご自身の責任においてご判断ください。